
算数の模試で点数が取れません…。どうすれば点数が上がるのかしら?点数アップの方法を教えてください。
このような悩み・疑問にお答えします。
この記事の内容
- 【中学受験】算数の模試で受験生がやりがちな3つのミス
この記事を書いている筆者は、塾講師・家庭教師での中学受験の指導歴19年ほど。これまでに、1,000人以上の受験生を指導してきました。
この記事では、そんな筆者の経験を踏まえて、算数の模試で受験生がやりがちな3つのミスを改善策とセットで紹介します。
※算数の模試の結果にお悩みの受験生の保護者や、算数の模試の点数アップの方法を知りたい方に参考になる記事です。
【中学受験】算数の模試で受験生がやりがちな3つのミス

進学塾の公開模試をはじめ、中学受験の模試は難易度が高いテストばかりです。なので、模試の点数が取れずに悩んでいる受験生や保護者も少なくないと思います。
もちろん、模試に向けた対策も重要なのですが、それ以前に多くの受験生が誤った解き方をしています。特に、算数の模試ではその傾向が強く、解き方を改善するだけでも、個人的にはプラス10点は簡単にアップすると思います。
そこで、算数の模試で受験生がやりがちな3つのミスを改善策とセットで紹介していこうと思います。
算数の模試でやりがちな3つのミス
- やりがちなミス①:狭いスペースで筆算している
- やりがちなミス②:全問解こうとしている
- やりがちなミス③:大問1の計算問題を2周していない
上記の3点が、受験生の問題用紙や答案用紙でよく目にする「やりがちなミス」です。
具体的なミスの内容と、その改善策を見ていきましょう。
やりがちなミス①:狭いスペースで筆算している
受験生に最も多いミスは、「狭いスペースで筆算している」です。(←おそらく、ほとんどの受験生がそうでしょう)
大問1の計算問題や、大問2の一行問題での筆算を狭いスペースでしている受験生をよく見かけます。特に、大問2の一行問題では、筆算が問題文に被っている受験生も珍しくありません。
そのせいで、本来正解できる問題を計算ミスで不正解になってしまっているのです。
筆算は「問題用紙の裏」に大きく!
筆者が、普段から受験生に意識付けさせているのは、「筆算は『問題用紙の裏』に大きく書きなさい」です。
せっかく問題用紙の裏に広いスペースがあるのに、わざわざ問題文の間の狭いスペースで筆算する必要はありません。問題用紙の裏の広いスペースで、大きな字で筆算を書く習慣を定着させてください。これだけで、計算ミスが減って点数アップが期待できますよ!
やりがちなミス②:全問解こうとしている
中学受験の公開模試は、偏差値70前後の最難関校を志望する受験生にも対応した、難易度が高い模試です。
にも関わらず、ほとんどの受験生が全問解こうとするので、超難問に時間を奪われ、本来解くべき問題に手をつけずに筆を置いています。
ちなみに、算数の模試で言えば、大問4〜大問6の「最後の小問」(※(1)〜(4)の4問なら、最後の(4)のことです)が超難問の可能性が高いと言えます。
※ぜひ一度、答案と一緒に返却された資料の「設問別の正答率」を確認してみてください。大問4以降の「最後の小問」は、正答率5%未満なことがほとんどです。
こうした超難問は、基本的には手をつけてはいけません。もし、お子さまの問題用紙や答案用紙を見て手を出しているなら、解けない問題に時間を奪われている恐れがあります。
大問4以降の「最後の小問」は捨てよ
筆者が、普段から受験生に意識付けさせているのは、「大問4以降の「最後の小問」は捨てなさい!」です。極端に聞こえるかもしれませんが、これくらい大胆に意識した方が、結果的に点数アップに繋がります。
受験生本人も、大問4以降の「最後の小問」は「解いても正解できない」とはじめから言われた方が、気持ちにも余裕が生まれます。これで、「時間に追われて焦った」とか、「時間が足りなかった」といった模試あるあるから解放されます。
やりがちなミス③:大問1の計算問題を2周していない
大問4以降の「最後の小問」を捨てた分、余った時間でしてほしいのが、「大問1の計算問題を2周する」です。なぜなら、多くの受験生が、比較的易しい大問1の計算問題を落としているからです。
そんな計算問題を落としているなら、思い切って2周解いても良いと、個人的には思います。(おそらく、ほとんどの受験生が1周しか解きません)
大問1の計算問題は全問正解が必須!
筆者が、普段から受験生に意識付けさせているのは、「大問1の計算問題は全問正解、絶対!」です。(←これは、入学試験でも同じです)
そのためなら、余った時間で計算問題を2周しても構わないと伝えています。
難しい問題を正解することより、解ける問題を確実に正解することが、点数アップの鉄則です。ぜひ、この機会に意識を変えましょう!
まとめ:さぁ、戦略を立てよう!

というわけで、今回は以上です。
算数の模試で受験生がやりがちな3つのミスを改善策とセットで紹介しました。筆者の経験では、この3つのミスを改善するだけで、多くの受験生が一気に点数アップしました。
お子さまにも該当するようなら、ぜひ次回の模試から試してほしいと思います。きっと、+10点、うまくいけばそれ以上の点数アップが期待できると思います。
また、この記事で紹介した改善策は、あくまでも筆者の経験に基づく一個人の意見です。ぜひ、お子さまと話し合って、独自の戦略を立ててほしいと思います。ただやみくもに勉強するのではなく、どうすれば点数が取れるのかを考えることが大切です。
この記事が、そのヒントになれば幸いです。
最後に、関連記事をまとめつつ、記事を終えたいと思います。
模試の点数がアップする解き方
【中学受験】公開模試の点数がアップする解き方【ポイントは3つ】
中学受験の公開模試は、偏差値70超の最難関校を志望する受験生にも対応した難易度MAXのテストです。そんな公開模試は、頭から順に解いてはいけません。公開模試ならではの解き方のテクニックが必要です。
公開模試の結果が悪い時の対処法
【中学受験】公開模試の結果が悪い時の3つの対処法【プロが解説】
公開模試の結果が悪い時の対処法を知りたい方向け。この記事では、中学受験の指導歴19年の筆者が、公開模試の結果が悪い原因とその対処法について解説しています。

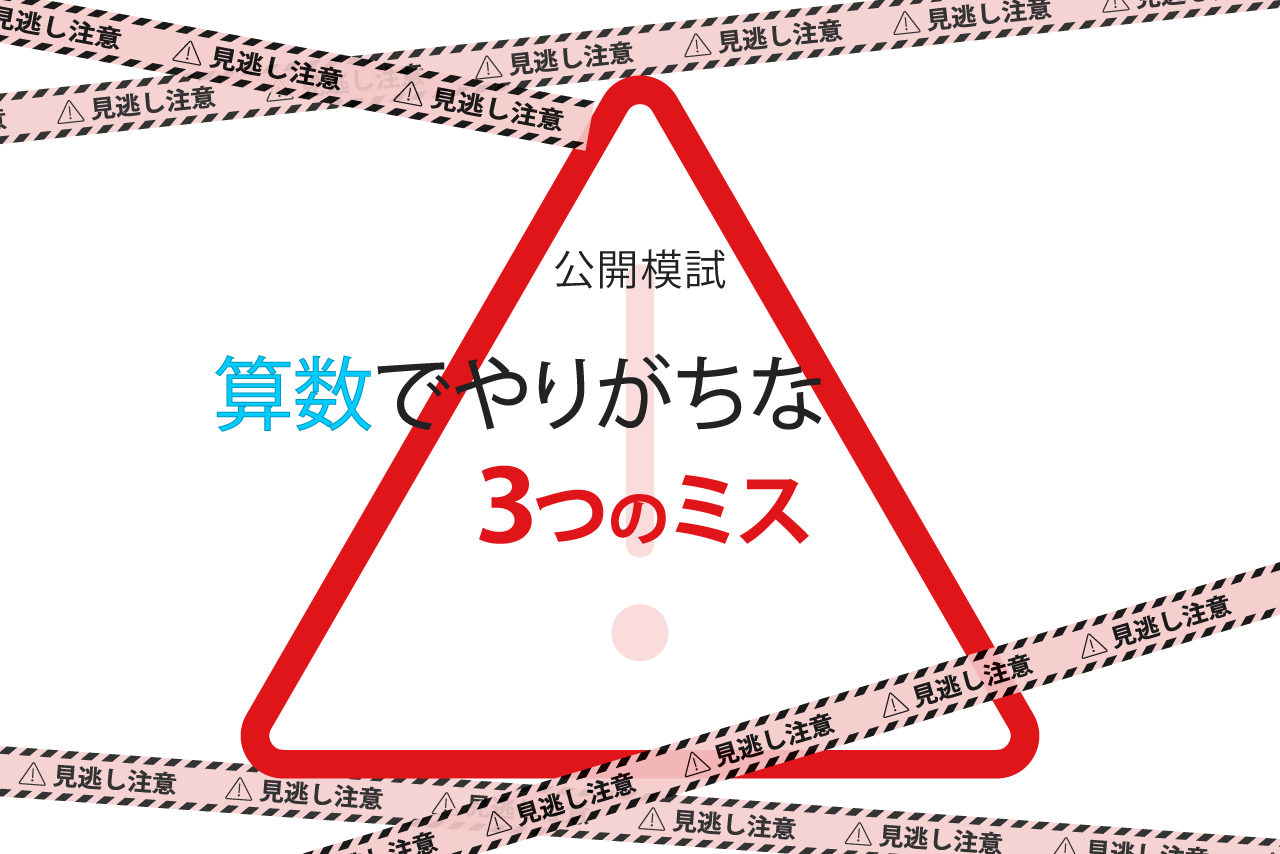



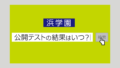

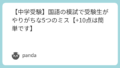

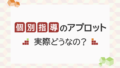

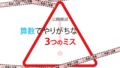


コメント