
国語の模試で点数が取れません…。どうすれば点数が上がるのかしら?点数アップの方法を教えてください。
このような悩み・疑問にお答えします。
この記事の内容
- 【中学受験】国語の模試で受験生がやりがちな5つのミス
この記事を書いている筆者は、塾講師・家庭教師での中学受験の指導歴19年ほど。これまでに、1,000人以上の受験生を指導してきました。
この記事では、そんな筆者の経験を踏まえて、国語の模試で受験生がやりがちな5つのミスを改善策とセットで紹介します。
※中学受験の国語の成績にお悩みの受験生やその保護者の方は、ぜひ参考にしてみてください。
【中学受験】国語の模試で受験生がやりがちな5つのミス

早速ですが、国語の公開模試で多くの受験生がやりがちな5つのミスを紹介していきます。
お子さまに該当しないか、チェックしてみてください。
受験生がやりがちな5つのミス
- やりがちなミス①:全問解こうとしている
- やりがちなミス②:文章を読まずにいきなり設問を解いている
- やりがちなミス③:マーキングをしていない
- やりがちなミス④:選択問題で消去法を使っていない
- やりがちなミス⑤:注釈を読んでいない
上記の通りです。
それぞれのミスについて、詳しく見ていきましょう。
やりがちなミス①:全問解こうとしている
中学受験の模試は、偏差値70超の最難関校を志望する受験生も受験する、難易度が高いテストです。
そんな模試には正答率5%ほどの超難問が混ざっています。当然、最難関校を志望しない限り、超難問を解く必要はありません。
とはいえ、受験生本人が超難問を見分けるのは簡単ではありません。そこで、下記の2点を意識して解いてみてください。
- 難しいと感じたら後回しにする
- 記述問題は最後に解く
特に、記述問題は時間が必要な上に、正答率が低いことがほとんどです。
模試は時間との勝負なので、答案用紙を埋めていくことを最優先に考えます。簡単な問題から解いていくことがポイントです。
なお、点数がアップする模試の解き方については「【中学受験】公開模試の点数がアップする解き方【ポイントは3つ】」の記事で解説しています。そちらもご参照ください。
【中学受験】公開模試の点数がアップする解き方【ポイントは3つ】
中学受験の公開模試は、偏差値70超の最難関校を志望する受験生にも対応した難易度MAXのテストです。そんな公開模試は、頭から順に解いてはいけません。公開模試ならではの解き方のテクニックが必要です。
やりがちなミス②:文章を読まずにいきなり設問を解いている
受験生に多いのが、文章を読まずにいきなり設問を解く解き方です。こうした解き方を塾で指導された受験生も少なくないはず。
もちろん、誤った解き方ではないのですが、中学生ならまだしも、多くの小学生にとっては難易度が高すぎると思います。
なぜなら、文章を読まずにいきなり解けるほど、模試は簡単ではないからです。
文章を読みながら設問を解いていく
では、どう解けば良いのかというと、文章を読みながら設問を解いていく方法がベストです。
そこまでに読んだ文章の中に答えやヒントがない場合は、設問内容を意識しながら続きを読み、答えやヒントが見つかれば設問に戻って答案します。
このように解けば、文章をすべて読むことになるので、試験後に「文章の内容がよくわからなかった」みたいなことにはなりません。しかも、文章を読みながら解くので、時間が足りなくなるリスクも回避できます。
筆者の知る限りでは、最も効率の良い解き方だと思います。
やりがちなミス③:マーキングをしていない
たまに、文章に何の書き込みもない、きれいな問題用紙を見かけます。
しかし、これではいけません。なぜなら、模試の文章は長く、一度読んだくらいでは、どこに何が書いてあったのかを記憶できないからです。
設問によっては、当該の傍線部の近くに答えやヒントがあるとは限りません。(※ちなみに、入試問題ほどこの傾向が強いですね)
だから、文章を読みながら重要に感じた語句や箇所を丸で囲ったり、線を引っ張っていかなければいけません。(これをマーキングといいます)
参考までに、マーキング必須の語句や箇所をまとめておきます。
マーキング必須の語句・箇所
- 登場人物や場所の名前(物語文)
- 時間や場面が変わる箇所(物語文)
- 感情に関する箇所(物語文)
- 「しかし」や「つまり」などの接続詞(説明文)
- 「と思います」などの筆者の考え(説明文)
まずは、上記を5点を意識しながらマーキングをしてみてください。きっと、設問を解く際のサポートになるはずです。
ただし、マーキングはたくさんすれば良いわけではありません。必要最小限で構いません。
気になる方は、筆者が必要だと思う最低限のマーキングについて解説した、「【中学受験】国語の長文読解に必要なテクニック【3つだけです】」の記事をご参照ください。
【中学受験】国語の長文読解に必要なテクニック【3つだけです】
国語の長文読解では、文章を読みながら重要な語句や箇所を丸で囲ったり、線を引っ張る「マーキング」が必須です。この記事では、受験生がまず押さえるべき必須マーキング3つを紹介しています。
やりがちなミス④:選択問題で消去法を使っていない
模試の選択問題は4択か5択であることがほとんどです。そして、一度読んでも「これが正解だ!」と1つに断定できることは、残念ながらまずありません。
だから、5択の中から1つを選ぶという解き方ではなかなか正解できません。しかし、ほとんどの受験生はいきなり1つを選ぼうとして失敗しています。
まずは、2択まで絞ろう!
では、どうすれば正解を選べるかというと、まずは消去法で2択まで絞ります。
そして、最後に残った2択から、文章の内容と照らし合わせて吟味した上で、1つに絞ります。
こうすれば、5択ではなく実質は2択なので、それだけ正解する確率が上がるわけです。
なお、最後の1つに絞る際には、文章の内容から根拠となる箇所を必ず見つけてください。何気なく選ぶのではなく、「ここに書いているから選んだ」と言えなければいけません。
やりがちなミス⑤:注釈を読んでいない
模試の文章は、小学生どころか大人でさえも知らないような語句で溢れています。
参考までに、大手進学塾の浜学園公開テスト(小5)の文章に含まれていた語句をご紹介します。
- ニッチ:隙間を意味する語
- 人道的:人道主義の立場にかなったさま
- まことしやか:事実や内心をつくろって本当めかす有様や態度
- 当惑:事に当たってどうしてよいかわからず、とまどうこと
- エビデンス:根拠、証拠、裏づけ
- ダイバーシティー:多様性
- おざなり:その場かぎりのまにあわせ。いい加減
- パンデミック:感染症や伝染病の世界的大流行
上記のような語句を知らないと文章の内容を理解できません。
だから、注釈を読まなければほぼ100%理解できません。それどころか、わざわざ注釈を付けているということは、それだけ重要な語句だということです。
そんな注釈を読まずして、文章を理解できるはずがありません。注釈のマーク(※)があれば、必ず注釈を読んでください。そして、語句の意味を理解した上で続きを読む習慣を定着させてください。
まとめ

以上、中学受験の国語の模試で受験生がやりがちな5つのミスを改善策とセットで紹介しました。
もう一度、おさらいしておきましょう。
受験生がやりがちな5つのミス
- やりがちなミス①:全問解こうとしている
- やりがちなミス②:文章を読まずにいきなり設問を解いている
- やりがちなミス③:マーキングをしていない
- やりがちなミス④:選択問題で消去法を使っていない
- やりがちなミス⑤:注釈を読んでいない
お子さまに該当するものがあれば、ぜひ本人に伝えてあげてください。改善するだけで+10点は簡単ですよ。
最後に、模試の点数アップに役立つ関連記事をまとめておきますので、そちらもぜひ!
国語の成績を上げる方法
【中学受験】国語の成績が上がらない2つの理由【苦手克服の方法も解説】
国語の成績にお悩みの受験生とその保護者の方向け。この記事では、国語の成績が上がらない2つの理由と、苦手克服の方法について解説しています。
模試の点数がアップする解き方
【中学受験】公開模試の点数がアップする解き方【ポイントは3つ】
中学受験の公開模試は、偏差値70超の最難関校を志望する受験生にも対応した難易度MAXのテストです。そんな公開模試は、頭から順に解いてはいけません。公開模試ならではの解き方のテクニックが必要です。
公開模試の結果が悪い時の対処法
【中学受験】公開模試の結果が悪い時の3つの対処法【プロが解説】
公開模試の結果が悪い時の対処法を知りたい方向け。この記事では、中学受験の指導歴19年の筆者が、公開模試の結果が悪い原因とその対処法について解説しています。

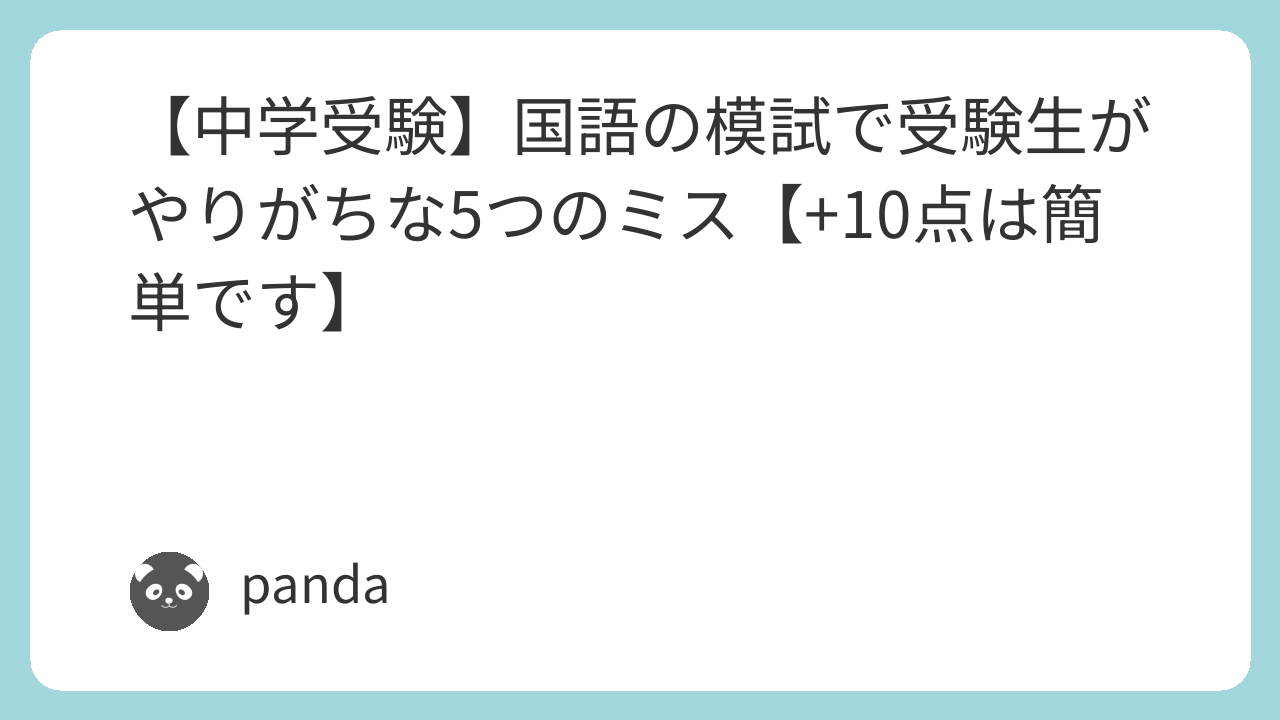



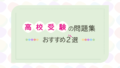

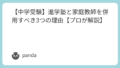
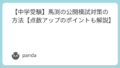

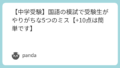


コメント