
国語の長文読解が苦手です。参考書や問題集を使っても成績が上がりません。長文読解に必要なテクニックを教えてください。
このような悩み・疑問にお答えします。
この記事の内容
記事の信頼性
この記事を書いている筆者は、塾講師・家庭教師での中学受験の指導歴19年ほど。これまでに、国語の長文読解が苦手な受験生を数多く指導してきました。
この記事では、そんな筆者の経験を踏まえて、長文読解に必要なテクニックについて解説します。また、長文読解で時間が足りない原因や、長文読解を克服するためのコツについても解説します。
※筆者が実際に、受験生に指導しているテクニックを公開します。参考書や問題集を解いても長文読解を克服できない受験生は、ぜひ参考にしてみてください。
【中学受験】国語の長文読解に必要なテクニック【3つだけです】

長文読解を克服するために、参考書や問題集を購入される受験生の保護者も少なくないと思います。
しかし、こうした参考書や問題集を使っても、長文読解はなかなか克服できません。
その理由は、参考書や問題集で紹介されている長文読解のテクニックが多すぎるからです。
【参考書・問題集】紹介されているテクニックが多すぎる
中学受験の国語の参考書や問題集では、長文読解を解く際に使えるテクニックを20も30も紹介しています。
そのほとんどは、ある決まりに従って文章に線を引いたり、丸や四角で語句を囲む、「マーキング」と呼ばれるテクニックです。
しかし、小学生である受験生がこうしたテクニックをすべて習得することは、ほぼ不可能と言っても過言ではありません。
マーキングが負担になることも
実際に、こうしたテクニックを習得しようとして、
- テクニックを覚えきれない
- マーキングが機械的な作業になっている
- かえって文章の内容が頭に入ってこない
などの失敗をしている受験生を数多く目にしてきました。
この失敗からわかることは、「こうしたテクニックは、すべての受験生にとって有効な方法であるとは限らない」ということです。
文章の内容を理解するために行うマーキングが、結果的には受験生にとっての負担になってしまうことがあるのです。
長文読解に必要なテクニック【3つだけです】
とはいえ、マーキングは長文読解では非常に重要なテクニックです。
そこで、筆者が受験生におすすめしているのは、「マーキングするものを3つだけに限定する」という方法です。
- マーキング①:登場人物と繰り返し出てくる語句を囲む
- マーキング②:筆者の考えに線を引く
- マーキング③:重要だと感じた箇所に線を引く
上記の通り。
それぞれのマーキングについて、詳しく解説します。
マーキング①:登場人物と繰り返し出てくる語句を囲む
まずは、囲む語句を絞ります。
物語文では登場人物に、説明文では繰り返し出てくる語句のみを囲みます。
※ちなみに、丸、四角のどちらで囲っても構いません。
マーキング②:筆者の考えに線を引く
次に、説明文での筆者の考えに線を引きます。
そして、その内容さえ分かれば、文章の全体像をつかむことができます。実際、中学受験では筆者の主張を答えさせる問題が多いですね。
マーキング③:重要だと感じた箇所に線を引く
最後に、受験生自身が重要だと感じた箇所にも線を引きましょう。
自分で考えて線を引くことで、どこが重要なのか感覚的にわかるようになっていきます。
その上で、下記の箇所に気づけるようになることを目指してください。
- 物語文:登場人物の感情が動いた箇所
- 物語文:時間や場面が変わった箇所
- 説明文:同じ内容を別の文で表現した箇所
- 説明文:反対の意見を述べた箇所
上記のような箇所は、すぐには気づけません。しかし、それを見つけることに集中しすぎると、かえって文章の内容が頭に入ってきません。
そこで、初めは自分が重要だと感じた箇所に線を引くことから始めます。やがて、「どこが重要な箇所なのか」を自分で気づけるようになります。
長文読解におすすめな参考書3冊
参考までに、筆者が読みあさった参考書の中からおすすめの3冊をまとめておきます。
文章読解の鉄則
最難関校の上位校を志望する受験生向けの1冊。筆者がマーキングの参考にしている参考書です。ただし、紹介しているテクニックが多いので、その中から必要なものだけを選ぶことをおすすめします。
記述問題の徹底攻略
記述問題が苦手な受験生におすすめな1冊。本文中から正しく抜き出す方法や正しい文章で記述する方法が学べます。
親子で身につける入試問題文の読み方
長文読解の「答えのヒント」はすべて文章中にあり、その見つけ方を学習できる参考書。親子で一緒に学習できるので、じっくりトレーニングしたい方におすすめです。
「試験時間が足りない」の原因は、語彙力の不足です


公開テストの試験時間が足りません…。
こんな声をよく耳にします。
その原因の多くは、長文読解に必要な語彙力が不足していることです。
【長文読解】語句の意味を理解していく作業です
長文読解では、文章の内容を理解しなければ設問を正解できません。
なので、文章で目にした語句の意味を短時間で理解していく必要があります。
どのような語彙力が必要なのか?
ここでは、筆者が指導している、大手進学塾「浜学園」の公開テスト(小5)に含まれていた語句をご紹介します。
- ニッチ:隙間を意味する語
- 人道的:人道主義の立場にかなったさま
- まことしやか:事実や内心をつくろって本当めかす有様や態度
- 当惑:事に当たってどうしてよいかわからず、とまどうこと
- エビデンス:根拠、証拠、裏づけ
- ダイバーシティー:多様性
- おざなり:その場かぎりのまにあわせ。いい加減
- パンデミック:感染症や伝染病の世界的大流行
小学生が日常生活では耳にしない(目にしない)ような語句が、数多く含まれていますね。
こうした語彙力が不足しているなら、まずは語彙力を増やさなければいけません。語彙力の不足を解消しなければ、いつまで経っても長文読解の成績は上がりません。
語彙力アップのために読むべき参考書3冊
受験生が押さえておくべき語彙力が定着する参考書をまとめておきます。
中学受験ズバピタ国語(慣用句・ことわざ)
中学受験に必要な慣用句とことわざが学習できる1冊。ランクごとに分けて紹介しているので、志望校に合わせて暗記することをおすすめします。
中学受験ズバピタ国語(四字熟語)
中学受験に必要な四字熟語をランク別に学習できる1冊。ズバピタ国語の2冊で基本的な語彙力を網羅できます。
中学受験国語の必須語彙2800
進学塾の公開テストや入学試験の文章に含まれる語句までをカバーできる1冊。ランク分けして語句を紹介しているので、1冊だけ選ぶなら迷わずこの1冊を選ぶべし!
【長文読解】スピードアップにおすすめな方法
短期間で長文読解のスピードアップを目指したい受験生には、小学生新聞の購読がおすすめです。
その理由は、文章を読む習慣を定着させることで、記事(文章)の内容を短時間で理解できるようになるからです。
しかも、小学生新聞には中学受験レベルの語句が数多く含まれるので、語彙力アップにも繋がります。
なお、小学生新聞で国語の成績が上がる理由については、「【中学受験】小学生新聞で国語の成績が上がる3つの理由【おすすめも紹介】」の記事で解説しています。
【中学受験】小学生新聞で国語の成績が上がる3つの理由【おすすめも紹介】
国語の成績が悪い原因の1つに、文章を理解するのに必要な語彙力の不足が挙げられます。この記事では、小学生新聞の購読で語彙力の不足が解消され、国語の成績が上がる理由について解説しています。
【長文読解のコツ】克服する方法は簡単です

ここまでの内容をまとめると、長文読解を克服するためのコツは下記の2ステップです。
- ステップ①:語彙力を増やす
- ステップ②:3つに限定してマーキングをする
まずはステップ①から。
語彙力を増やすことで問題文の内容を短時間で理解できるようになります。このステップ①をクリアすることで、「試験時間が足りない」という問題が解決します。
次にステップ②です。
この記事でご紹介したように、「3つに限定して」マーキングしながら問題文を読みます。
まとめ

以上、国語の長文読解に必要なテクニックである、3つのマーキングについて解説しました。また、長文読解で時間が足りない原因や、長文読解を克服するためのコツについても解説しました。
繰り返しになりますが、中学受験の長文読解の参考書や問題集を使っても、長文読解はなかなか克服できません。お子さまがつまずいている原因を調べ、そこからアプローチしていく必要があります。
そのヒントとして、筆者が指導している内容である、「長文読解に必要な語彙力の習得と、最低限のマーキングテクニックを使った解き方」をご紹介しました。
この記事の内容が、多少なりとも参考になれば幸いです。
国語の成績を上げる方法
【中学受験】国語の成績が上がらない2つの理由【苦手克服の方法も解説】
国語の成績にお悩みの受験生とその保護者の方向け。この記事では、国語の成績が上がらない2つの理由と、苦手克服の方法について解説しています。
小学生新聞で国語の成績が上がる理由
【中学受験】小学生新聞で国語の成績が上がる3つの理由【おすすめも紹介】
国語の成績が悪い原因の1つに、文章を理解するのに必要な語彙力の不足が挙げられます。この記事では、小学生新聞の購読で語彙力の不足が解消され、国語の成績が上がる理由について解説しています。
国語の模試で受験生がやりがちなミス
【中学受験】国語の模試で受験生がやりがちな5つのミス【+10点は簡単です】
国語の模試の結果にお悩みの受験生の保護者や、国語の模試の点数アップの方法を知りたい方向け。この記事では、国語の模試で受験生がやりがちな5つのミスを改善策とセットで紹介しています。

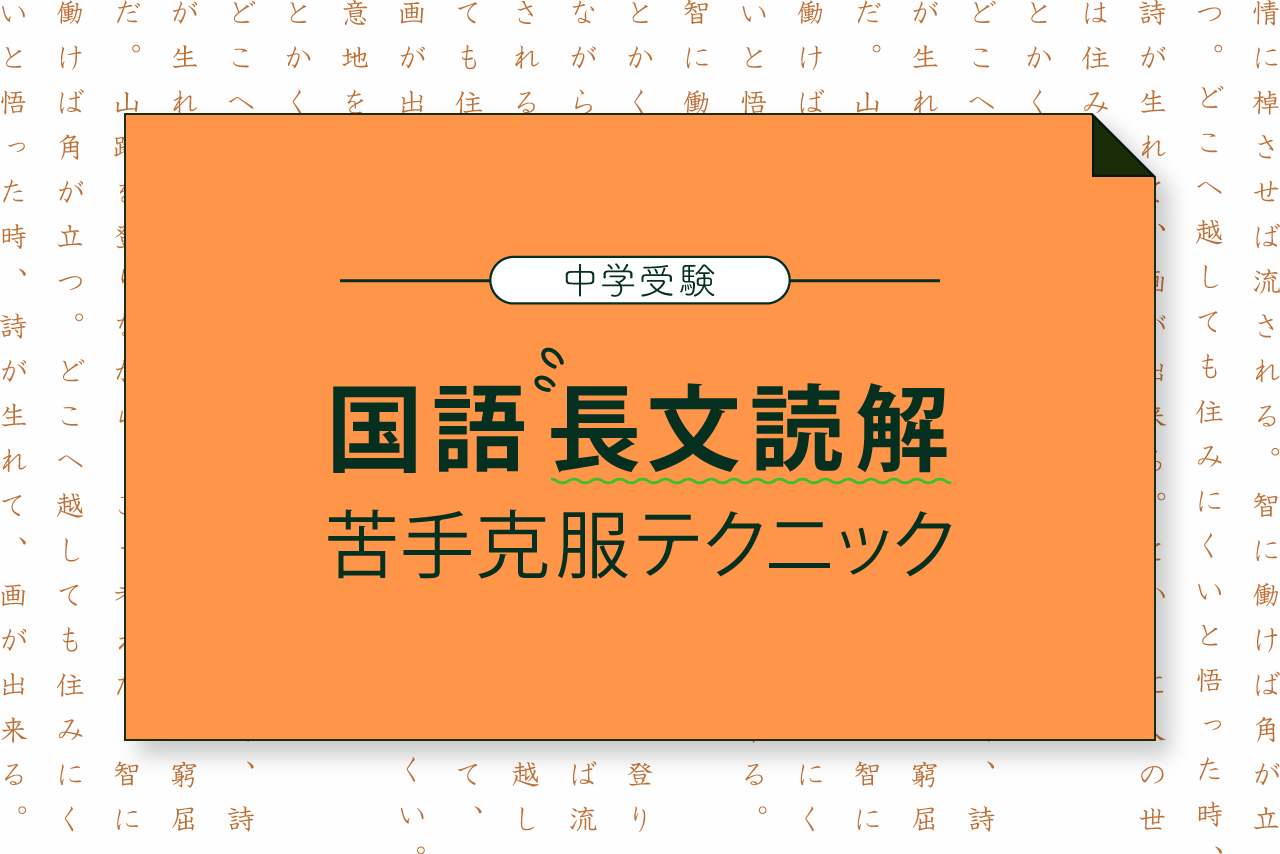












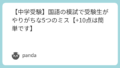

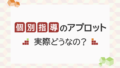


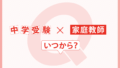

コメント