
副教科の内申点の上げ方を知りたいなぁ…。副教科の定期テストの勉強法は?おすすめの問題集も教えてください。
このような疑問にお答えします。
この記事の内容
記事の信頼性
この記事を書いている筆者は、塾講師・家庭教師での中学生の指導歴18年ほど。現在はプロ家庭教師として、副教科の定期テスト対策も指導しています。
この記事では、そんな筆者の経験を踏まえて、副教科の内申点の上げ方と定期テストの勉強法について解説します。また、副教科のテスト勉強におすすめな問題集も紹介します。
※この記事で紹介する勉強法は、筆者が家庭教師として実際に指導している、副教科の定期テスト対策の内容です。勉強法だけでなく注意点も解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
【中学生】副教科の内申点の上げ方

結論としては、定期テストで高得点を取れば内申点は上がります。
※注意点:副教科の成績は実技点だけでは決まりません
副教科の成績は、実技点だけで決まるわけではありません。実技点だけでなく、授業態度や提出物、そして何よりも定期テストの点数が大きく影響します。
【副教科の成績】実技点だけでは決まらない
あまりにも多くの中学生が誤解しているので、まずはここから解説します。
副教科の成績は、5教科の成績とは異なり実技点が影響します。(体育や音楽なら実技テスト、技術家庭科や美術なら作品の評価ですね)
しかし、実技点はあくまで評価の一部であり、すべてではありません。
もちろん、何を重視するのかは先生によって異なりますが、筆者の印象では実技点よりも定期テストの点数を重視している先生の方が多い気がします。
定期テストで高得点を取れば、内申点は簡単に上がる
本題に戻りますが、定期テストで高得点を取れば内申点は簡単に上がります。
ここでは、その理由について解説していきます。
内申点が簡単に上がる2つの理由
- 理由①:ほとんどの中学生が副教科のテスト勉強をしないから
- 理由②:定期テストでは大きな点数の差が生まれやすいから
それぞれの理由について、詳しく解説します。
理由①:ほどんどの中学生が副教科のテスト勉強をしないから
ほとんどの中学生が、副教科のテスト勉強は一夜漬けです。
学習塾でも5教科のテスト対策が中心で、副教科のテスト勉強は後回しです。
だから、副教科のテスト勉強を本気で頑張れば、割と簡単にクラスで上位が取れるはずです。
理由②:定期テストでは大きな点数の差が生まれやすいから
理由①でも解説した通り、ほとんどの中学生が副教科のテスト勉強は一夜漬けです。
そのため、成績優秀者でも副教科の定期テストでは足元をすくわれることも珍しくありません。そして、副教科を本気で勉強した人との間に、大きな点数の差が生まれやすくなります。
その結果、副教科では5教科よりも高得点者と低得点者との差が大きくなり、平均点が低くなる傾向があります。
副教科の定期テストの勉強法【おすすめ問題集も紹介】
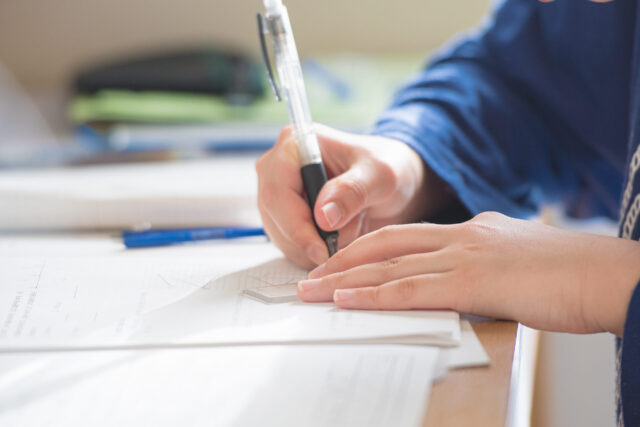
定期テストで高得点を取れば、副教科の内申点が簡単に上がる理由が理解できたかと思います。
ここからは、そんな副教科の定期テストで高得点を取るための勉強法について解説します。
※筆者の経験では、5教科を頑張る中学生ほど副教科のテスト勉強を後回しにしがちです。そんな自覚がある中学生は、特に注意が必要です。
【副教科のテスト勉強】基本は教科書とノートの見直し
副教科のテスト勉強の基本は、何と言っても教科書とノートの見直しです。
と言いますのも、定期テストの問題の9割以上が、教科書とノートから出題されるからです。
副教科のテスト勉強にも時間を割こう
ほとんどの中学生が一夜漬けだからこそ、一夜漬けでは追いつけないくらいテスト勉強に時間を割くことが大切です。
5教科と同じくらいの時間を割く必要はありませんが、5教科と同様に副教科を常に意識しながらテスト勉強に取り組みましょう。「副教科は後回し」ではいけません。
具体的な学習計画は下記の通り。
- テスト2週間前まで:教科書・ノートの見直し
- テスト2週間前~:教科書・ノートの重要語句をまとめる
- テスト1週間前~:重要語句の暗記
テスト2週間前までは、教科書やノートを見直す程度で構いません。
そして、テスト2週間前からは教科書やノートの重要語句をまとめます。ノートにまとめてもいいですが、個人的には重要語句に緑マーカーを引く感じで十分かと思います。
テスト1週間前からは、まとめた内容を(下記のような)赤シートを使って徹底的に暗記します。必要に応じて、問題集などを使って暗記チェックをすると良いでしょう。
副教科:おすすめの問題集2選
テスト1週間前からの重要語句の暗記では、暗記チェックに問題集を使うのがおすすめです。
おすすめ問題集
- おすすめ①:文理「中学教科書ワーク」
- おすすめ②:受験研究社「中学実技4科の総まとめ」
どちらも、「市販の問題集」を数多く出版している出版社のものです。
それぞれの特徴と、おすすめ理由を簡単にまとめておきます。
おすすめ①:文理「中学教科書ワーク」
すべての教科書に対応した、3年間使えるタイプの問題集。
教科別に販売されているので、苦手な教科の問題集を買いそろえたい中学生におすすめ。
一問一答と予想問題で構成されているので、この1冊があれば基本的には十分かと思います。
おすすめ②:受験研究社「中学実技4科の総まとめ」
こちらもすべての教科書に対応した、3年間使えるタイプの問題集。
1冊で実技4教科のテスト勉強ができるので、費用を安く抑えたい中学生におすすめ。
ただし、一問一答形式のみなので、重要語句のチェックはできますが、出題のされ方までは分かりません。
補足:副教科の評定5をとる方法

副教科で評定5をとるためには、実技テストはもちろんのことながら、定期テストで高得点をとることが必須です。
※ちなみに、評定5をとれるのは各教科ともクラスで2、3人です。
当然、定期テストでクラスの上位3位以内を目指すことは言うまでもありません。
学校の教科書に対応した問題集はない
定期テストで上位3位に入るためには、教科書やノートの見直しだけでなく、問題集を解いておく必要があります。
しかし、この記事で紹介した「市販の問題集」を含めて、それぞれの教科書に対応した問題集はありません。
※筆者の知る限り、それぞれの教科書に対応した(教科書準拠版の)問題集は販売されていません。
おすすめ:通信教育なら学校の教科書の復習ができる!
学校の教科書の復習をしたいなら、学校の教科書に対応した通信教育がおすすめです。
学校の教科書に対応した問題を解くことで、教科書やノートの理解度を確認することができます。
料金がかかるとはいえ、月額数千円で利用できるので、本気で評定5をとりたいなら検討してみる価値は十分にあるかと思います。
なお、学校の教科書に対応している通信教育は「【副教科】評定5には通信教育がおすすめな理由【おすすめ2社も紹介】」の記事にまとめておりまして、無料体験もあるので気になる方は検討されてはと思います。
【副教科】評定5には通信教育がおすすめな理由【おすすめ2社も紹介】
副教科で評定5をとりたい中学生向け。この記事では、副教科の評定5には通信教育がおすすめな理由について解説しています。また、副教科の定期テスト対策におすすめな通信教育も紹介しています。
というわけで、今回は以上です。
副教科の内申点の上げ方と定期テストの勉強法について解説しました。また、おすすめの問題集も紹介しました。
繰り返しになりますが、副教科の内申点を上げるためには定期テストで高得点を取ることがポイントです。
ほとんどの中学生が副教科のテスト勉強は一夜漬けなので、定期テストで上位を取ることは決して難しいことではありません。そして、クラスで上位3位以内に入れば、副教科の評定5も夢ではありません。
ぜひ、副教科のテスト勉強にガッツリ向き合ってみましょう!
この記事が、その参考になれば幸いです。











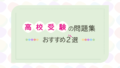

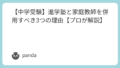
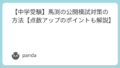

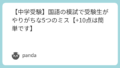




コメント