
公開テストの解き直しをしたいけれど、どうやってすればいいのかしら…。点数アップに繋がるいい方法を知りたいです。受験生本人が自分でできる、具体的な方法を教えてください。
このような疑問にお答えします。
この記事の内容
- 【自分でできる!】公開テストの点数が上がる「解き直し」の方法
- 要注意:解き直しをする際の3つの注意点
記事の信頼性
この記事を書いている筆者は、家庭教師での公開テスト対策の指導歴19年ほど。これまでに、100人以上の浜学園生に公開テストの解き直しを指導してきました。
この記事では、そんな筆者の経験を踏まえて、受験生本人が自分でできる公開テストの解き直しの方法について解説します。また、解き直しをする際の注意点についても解説します。
※浜学園の公開テストに限らず、どの公開テストでも同様の方法で解き直しができます。ぜひ参考にしてみてください。
【自分でできる!】公開テストの点数が上がる「解き直し」の方法

早速ですが、公開テストの解き直しの方法について解説していきます。
分かりやすく3ステップにまとめました。
解き直しの方法【3ステップ】
- ステップ①:不正解だった問題の正答率を確認する
- ステップ②:不正解だった問題をノートに解き直す
- ステップ③:正解できるまで繰り返し解く
ステップごとに詳しく解説していきます。
ステップ①:不正解だった問題の正答率を確認する
まずは、不正解だった問題の正答率を確認します。
※ちなみに、正答率は「試験結果の資料」の「科目別・答案結果」に載っています。
その中から、正答率50%以上の問題をピックアップしてください。
というわけで、不正解だった問題の中でも、正答率50%以上の問題だけを解き直します。
正答率50%未満の問題は後回し
正答率50%未満の問題は、解き直しに慣れてきたり、点数が上がってきてからでOKです。
ただし、永遠にスルーとはいきませんよ。特に、難関校を受験するなら、正答率30%台の問題まで解き直しをしてください。
目安がわからないという受験生は、浜学園の先生に相談することをおすすめします。
ステップ②:不正解だった問題をノートに解き直す
解き直し用のノート(通称、解き直しノート)を1冊作ってください。
※科目ごとにノートを分けても構いません。お好みでどうぞ!
そして、ステップ①でピックアップした問題をノートに解き直します。
ちなみに、自力で解く必要はありません。公開テストの解説やテキストなどを見ながらで構いません。
できれば問題文も貼っておこう!
自宅にプリンターがあるなら、問題文のコピーを貼っておくことをおすすめします。
※スマホで問題文を撮影して、プリンターで印刷してください。
理由は、後でノートを見直した時に「不正解だった問題」と「正解の解き方」がセットで分かるからです。
なお、教科別の「解き直しノート」の作り方を知りたい方は「【中学受験】模試・過去問の「解き直しノート」の作り方【簡単です】」の記事をどうぞ。
【中学受験】模試・過去問の「解き直しノート」の作り方【簡単です】
中学受験の模試や過去問の「解き直しノート」の作り方を知りたい方向け。この記事では、中学受験の指導歴19年の筆者が実際に受験生に指導している、「解き直しノート」の作り方について解説しています。
ステップ③:正解できるまで繰り返し解く
ノートに解き直しただけでは、公開テストの点数はアップしません。
理解できるまでノートを見直して、正解できるまで何度も解きましょう。不正解だった問題を正解できるようになるまでが解き直しです。
要注意:解き直しをする際の3つの注意点

筆者が日頃から受験生に伝えている注意点をまとめておきます。ぜひ、参考にしてみてください。
解き直しをする際の注意点
- 注意点①:答えの丸写しをしない
- 注意点②:わからない問題は先生に質問する
- 注意点③:「解き直しノート」を見直す
上記の3点です。
注意点①:答えの丸写しをしない
たまに、解き直しをして満足している受験生を見かけますが、解き直しの目的は「解けるようになること」です。
答えの丸写しをしていても、意味がありません。
もちろん、答えや解説を参考にしながら解き直しをしてもらって構いません。ただし、自分の言葉でまとめなければ、学力としては定着しませんよ。
何を書けばいいのかわからない受験生は、
- 何がわからなかったのか?
- どのようなミスをしたのか?
- 正しい解き方は?
- 次回、正解するためのポイントは?
を自分の言葉でノートにまとめてみましょう。
注意点②:わからない問題は先生に質問する
わからない問題を放置していても、学力は上がりません。ぜひ、塾の先生やチューターの先生に質問しましょう。
大変な作業ですが、これをするかしないかで大違い!わからない問題が減れば、志望校合格がグッと近づきます。反対に、わからない問題を放置していると、志望校合格は黄色信号です!
注意点③:「解き直しノート」を見直す
解き直しをしても、3日も経てば記憶はドンドン薄れていきます。そして、1カ月も経てば、すっかり忘れてしまいます。
なので、「解き直しノート」は常に持ち歩き、電車の中や教室など、空き時間に目を通すようにしてください。
まとめ:「解き直しノート」は受験生のバイブルです
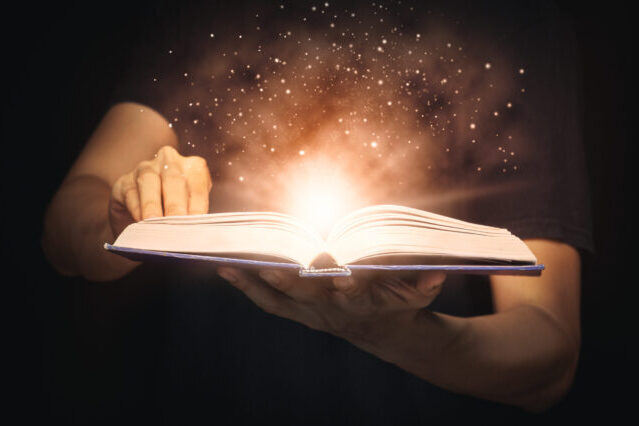
これは、筆者が受験生と解き直しをする際に話していることですが、「解き直しノート」は受験生のバイブルだと思っています。
なぜなら、「解き直しノート」の中には、受験生本人の苦手な問題が詰まっているからです。そして、「解き直しノート」を完全にマスターすれば、もはや鬼に金棒、恐れるものはありません。
入学試験の当日に、そんなバイブルを手にしたお子さまを想像してみてください。きっと、安心して送り出してあげられるはずです。
それを目標に、ぜひ最強のバイブルを作ってほしいと思います。
「解き直しノート」の作り方
【中学受験】模試・過去問の「解き直しノート」の作り方【簡単です】
中学受験の模試や過去問の「解き直しノート」の作り方を知りたい方向け。この記事では、中学受験の指導歴19年の筆者が実際に受験生に指導している、「解き直しノート」の作り方について解説しています。
模試の点数がアップする解き方
【中学受験】公開模試の点数がアップする解き方【ポイントは3つ】
中学受験の公開模試は、偏差値70超の最難関校を志望する受験生にも対応した難易度MAXのテストです。そんな公開模試は、頭から順に解いてはいけません。公開模試ならではの解き方のテクニックが必要です。
公開模試の結果が悪い時の対処法
【中学受験】公開模試の結果が悪い時の3つの対処法【プロが解説】
公開模試の結果が悪い時の対処法を知りたい方向け。この記事では、中学受験の指導歴19年の筆者が、公開模試の結果が悪い原因とその対処法について解説しています。

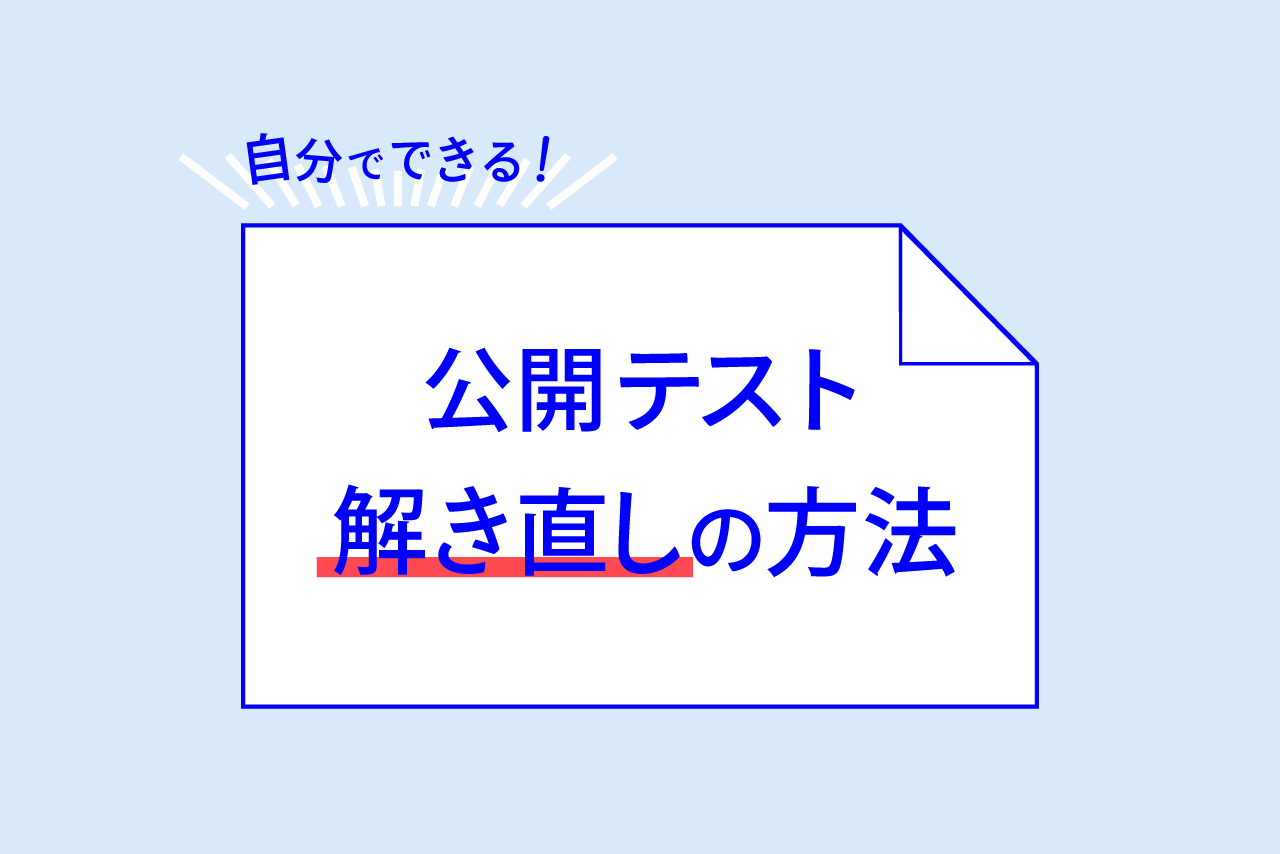



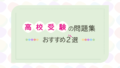

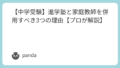
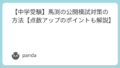

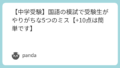


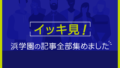

コメント