
夏休みの自由研究のテーマが決まらない…。どんなテーマを選べばいいのかなぁ…。おすすめのテーマとレポートの書き方を教えてください。
このような悩み・疑問にお答えします。
この記事の内容
- 「夏休みの自由研究」とは?
- 【テーマの選び方】ポイントは「なぜだろう?」
- 【夏休みの自由研究】筆者おすすめのテーマを紹介
- 【真似してOK!】上手なレポートの書き方
この記事を書いている筆者は塾講師・家庭教師での小・中・高校生の指導歴19年ほど。(中学と高校の理科の教員免許を持っています)夏休みの自由研究について、実際に小・中学生の疑問・質問に答えてきました。
この記事では、そんな筆者の経験を踏まえて、筆者がおすすめする自由研究のテーマをご紹介します。また、自由研究のレポートの書き方についても解説します。
この記事を読めば、夏休みの自由研究の悩みはあっという間に解決します!
「夏休みの自由研究」とは?

夏休みの自由研究について、ご存知でない方向けに簡単に説明しておきます。(※ご存知の方はスキップしてください)
小・中学校の夏休みの宿題です
小・中学校の夏休みの宿題として出されるのが自由研究です。
※もちろん、学校にもよります。
【自由研究】テーマがなかなか決まらない
夏休みに入ると、小・中学生から自由研究に関する質問をよくされます。
- 自由研究のテーマが決まりません。
- おすすめのテーマを教えてください。
- レポートの書き方が分かりません。
こんな感じですね。
決められたテーマについて調べる普段の宿題とは違い、テーマを自分で選ぶ自由研究は、小・中学生には慣れないかもしれません。また、何か難しい実験をしなければいけないと思っている小・中学生も多いように感じます。
そこで、自由研究のテーマの選び方から研究の方法、レポートの書き方までをまとめて解説していきます。
【テーマの選び方】ポイントは「なぜだろう?」

ここでは、自由研究のテーマの選び方について解説します。
ポイントは下記の4つです。
- ポイント①:興味がある分野からテーマを探す
- ポイント②:「なぜだろう?」と思うことを探す
- ポイント③:夏休みにしかできないテーマを選ぶ
- ポイント④:実験や観察が必要なテーマを選ぶ
それぞれのポイントについて、詳しく解説していきます。
ポイント①:興味がある分野からテーマを探す
自由研究におっくうになる小・中学生の多くが、自由研究そのものに興味がありません。しかし、それでは良い研究などできるはずがありません。
そこで、自由研究のテーマは、なるべく興味がある分野から選ぶようにしてください。
興味がある内容について調べよう!
まずは、日常生活の中で興味があることを思い浮かべてみましょう。その内容をヒントに、関連のある現象や事物について調べれば良いのです。
ポイント②:「なぜだろう?」と思うことを探す
続いて、その中から自分が「なぜだろう?」と疑問に感じることがないか、考えてみてください。
- なぜ、ボールは自然に止まるんだろう?
- なぜ、夏になるとセミが鳴くんだろう?
- なぜ、流れ星が流れるんだろう?
- なぜ、カビ取り剤でカビが取れるんだろう?
- なぜ、ホットケーキは膨らむんだろう?
このような「なぜだろう?」の答えを調べるだけでも、自由研究のテーマとしては成り立ちます。
具体的には、下記のようなテーマです。
- ボールの速さと止まるまでの距離の関係
- セミの観察と生態
- 流れ星の観察と正体
- カビ取り剤の成分とカビの正体
- ホットケーキミックスの成分
少し意外に感じるかもしれませんが、文字通り自由に研究して良いのですから、気にしない気にしない!
ポイント③:夏休みにしかできないテーマを選ぶ
いくつか候補があるなら、夏休みにしかできないようなテーマを選びましょう。その理由は、自由研究には「夏休みにしかできないようなテーマを選んでほしい」という、学校の先生の願いが込められているからです。
週末にできる実験や、インターネットで調べればすぐに分かる内容ではなく、時間をかけることで実感・確認できるようなテーマがベストです。
ポイント④:実験や観察が必要なテーマを選ぶ
自由研究では、実験や観察を行うことが大切です。疑問に感じたことを調べることも研究ですが、できれば実験で検証したり、観察で確認することをおすすめします。
反対に、実験や観察が不要なテーマを選んでしまうと、調べたことを実験で検証したり、観察で確認できません。
【夏休みの自由研究】筆者おすすめのテーマを紹介

ここでは、理科の先生でもある筆者が、おすすめのテーマと自由研究の内容について解説します。
理科の先生イチオシ!自由研究のテーマは?
1つに絞るのは難しいですが、個人的におすすめなのは「月の満ち欠け」です。
確かに、私たちが普段から目にする月の形は様々ですし、見える時間帯も異なります。そこで、「月の満ち欠け」について調べたり観察することで、理解を深めようというわけです。
このように、身近な自然現象に関する疑問について研究する意義は大きいですね。しかも、実際に観察して確認できるので、自由研究のテーマにピッタリかと思います。
自由研究の内容は?

自由研究って何をしたらいいの?
こんな疑問を抱いている小・中学生も多いはず。
そこで、「月の満ち欠け」を例に、自由研究の内容について解説します。
自由研究の内容【することは3つ】
- 内容①:本やインターネットなどで調べる
- 内容②:実験や観察で確認する
- 内容③:調べたこと・確認したことについて考察する
内容①:本やインターネットなどで調べる
まずは、「月の満ち欠け」について、疑問に思っていることをインターネットや本で調べてみます。
- なぜ、月の形が変わるのか?
- 月の満ち欠けの周期は?
疑問に思っていることの答えだけでなく、調べる中で分かったことがあれば、そのことについてもまとめると良いですね。
※なお、調べる時に使った本やサイトのURLはレポートに参考文献として載せるので、メモをお忘れなく!
内容②:実験や観察で確認する
次に、内容①で調べたことについて、実際に実験や観察で確認します。
「月の満ち欠け」の場合なら、調べたことが本当にその通りなのか、観察して確認します。
観察する内容
- 数時間、月の動きを観察する→形や速さを確認する
- 1カ月間、月を観察する→月の満ち欠けの周期を確認する
- 1カ月間、毎晩同じ時刻に同じ方角を観察する→月の位置の変化を確認する
観察する内容は、内容①で「月の満ち欠け」について調べて分かったことをヒントに考えましょう。
内容③:調べたこと・確認したことについて考察する
小学生にとっては、考察という言葉は難しいかもしれません。なので、小学生は考察を省略しても構いません。
考察の内容
- 調べたことと実験・観察した結果が一致しているかを検証する
- 一致していない場合は、その原因を予想する
- 実験・観察ができなかった場合は、結果を予想する
上記の内容を自分なりに考えて、レポートのまとめると良いでしょう。
ちなみに、「月の満ち欠け」の観察では、天候によっては観察できない日がありますね。そんな時は、前後の日の記録から、観察できなかった日の記録を予想します。
実験も同じですね。何らかの理由で実験が失敗したら、その原因を考えます。そして、実験が成功していたら得られたであろう、正しい結果を予想します。
自由研究のテーマ選びに役立つ書籍
自由研究のテーマ選びに役立つ書籍をまとめておきます。
小学生のおもしろ科学実験
小学生におすすめなテーマとその方法をまとめた1冊。
小学生でもできるような、簡単かつおもしろいテーマを集めています。
自由研究「中学の理科」
中学生におすすめなテーマとその方法をまとめた1冊。
クラスの誰とも被らないような、おもしろいテーマが満載です。
【真似してOK!】上手なレポートの書き方

ここでは、自由研究のレポートの書き方について解説します。
※ただし、学校の先生から書き方を指定されているなら、それに従って自由研究のレポートを作成してくださいね。
自由研究のレポートの書き方
自由研究のレポートは、項目に分けてまとめていきます。
ここでは、「月の満ち欠け」のレポートを例に、項目ごとの具体的なまとめ方について解説します。
レポートの項目
- (1)テーマ
- (2)目的
- (3)実験器具・準備物
- (4)実験方法・観察方法
- (5)実験結果・観察結果
- (6)考察
- (7)感想・まとめ
- 参考文献
それぞれの項目ごとに、解説していきます。
(1)テーマ
まずは、自由研究のテーマですね。
(2)目的
続いて、研究の目的です。
- なぜ、その研究をするのか?
- 何を知りたいのか?
- 何を調べたいのか?
など、動機が分かるように書きましょう。
(3)実験器具・準備物
実験や観察に必要な実験器具や準備物を書きます。
レポートを読んだ人が、同じ実験や観察を行うために必要なものをすべて書きます。
(4)実験方法・観察方法
実験や観察の方法を番号を付けて説明します。
- 観察1:月の満ち欠け
1-1 月が観察できる夜に、月をカメラで撮影し、月の形を記録する。
1-2 その後、1カ月にわたって毎晩同じ時刻に月をカメラで撮影し、月の形を記録する。 - 観察2:月の動き
2-1 一晩の間に月がどのように動いているのかを調べる。
2-2 1時間ごとに月をカメラで撮影し、月の位置を記録する。
(5)実験結果・観察結果
実験結果や観察結果をまとめます。
スケッチしたものや写真で撮影したものがあれば、レポートに貼ります。特に、時間の経過とともに変化がある記録は、図や写真を入れるようにしましょう。
結果のまとめ方を考えながら、実験や観察ができればなお良しですね。
- 月の写真を並べて、1日おきの月の形の変化をまとめる。
- 同じ時刻の月の位置の変化を1日おきにまとめる。
- 一晩の1時間おきの月の位置をまとめる。
(6)考察
実験結果や観察結果が、調べた内容(理論)と一致するかを検証します。
教科書や参考書、図鑑、インターネット等を使って、実験結果や観察結果が正しいかどうか確認します。
結果が理論と一致するなら、それを確認できたことを書きます。一致しないなら、その原因について考えたことや調べたことを書きます。
- 月の満ち欠けは、約〇日の周期で起こることが確認できた。
- 東の空から月の出し、南中したのち、西の空に月の入りすることが確認できた。
- 月の出の時間と月の入り時間は、毎日〇時間ずつずれていた。
- 8月×日は曇っていて月は観察できなかったが、前日と翌日の記録から図のように予想した。
(7)感想・まとめ
小学生の自由研究なら感想で構いません。中学生以上は、下の例を参考に研究についてまとめましょう。
- 今回の自由研究では、「月の満ち欠けと動き」について約1カ月間にわたって観察を行った。「月の満ち欠け」については、実際に観察することで、学校で学習した内容をより深く理解できた。
- 「月の動き」については、月の出の時間が日々変わることを知らなかったので、月を観察できない日があり苦労した。
- また、昼の時間帯に月の出する日があり、インターネットや新聞に月の情報が掲載されている理由が分かった。
- 1カ月にわたって観察を行ったからこそ気付けたことも多く、自然界の法則に改めて興味を持った。
感想・まとめでは、研究の成果だけでなく、自分自身の率直な感想を書くと良いでしょう。
参考文献
最後に、自由研究に使用した書籍やインターネットのページURLを書きます。小学生の自由研究では省略しても構いません。
まとめ

というわけで、今回は以上です。
夏休みの自由研究について、おすすめのテーマとレポートの書き方について解説しました。
あくまでも参考にしつつ、自分なりに研究して、レポートを書けばOKです!大切なことは、あなた自身が興味・関心を持っていることについて研究してみることです。
そんな、あなたならではの自由研究のレポートを学校の先生は楽しみに待っているはずです。
最後に、自分でテーマを考えるのが苦手な小・中学生向けに、そのまま自由研究に使える商品を紹介しておきます。
自由研究おたすけキット「指紋を調べよう」
自分の指紋をとる実験と観察ができるキット。
解説の動画付きで、実験、観察、レポートを1日で完成できます。
わくわくサイエンスLabo「炎色反応」
物質を燃焼させた時の炎色反応の違いを調べる実験キット。
レポートの作り方の実例付きなので、ポイントも押さえられます。
理科実験キット「光の実験」
光の性質を確認できる実験キット。
2枚の凸レンズを使って、光の直進、反射、屈折を確認できます。
理科教材「ふりこのはたらき」
ふりこの周期を調べられる実験キット。
ふりこの長さやおもりの重さなど、条件を変えて実験できるので、どんな条件がふりこの周期に影響するのかを調べられます。



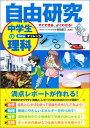







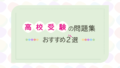

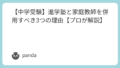
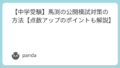

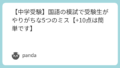




コメント