
志望校の過去問・赤本はいつから解けばいいんだろう…。何年分解いたらいいの?赤本のおすすめの使い方を教えてください。
このような疑問にお答えします。
この記事の内容
記事の信頼性
この記事を書いている筆者は、家庭教師・塾講師での高校受験の指導歴18年ほど。これまでに、1,000人以上の受験生を指導してきました。
この記事では、そんな筆者の経験を踏まえて、志望校の過去問・赤本のおすすめの使い方について解説します。また、筆者おすすめの過去問題集も紹介します。
※この記事を読むことで、志望校の赤本をいつから解けばいいのか、何年分解けばいいのかなど、赤本の使い方がわかります。
【高校受験】志望校の過去問・赤本はいつから?

結論からお話しすると、志望校の過去問(通称、赤本)は中3の冬休み以降から解き始めます。
と言いますのも、入学試験には中3・3学期の内容までが含まれるので、その範囲を学習しなければ解けないからです。
ちなみに、私立高校と公立高校の両方をダブル受験する受験生は、まずは(2月に受験する)私立・志望校の赤本から解き始めます。(3月に受験する)公立・志望校の赤本は、私立の入試が終わってから解き始めます。
なお、3学期の予習と過去問対策を含む冬休みの過ごし方については、「【高校受験】中3受験生の冬休みの過ごし方【おすすめ勉強法も解説】」の記事で解説しています。
【高校受験】中3受験生の冬休みの過ごし方【おすすめ勉強法も解説】
中3冬休みの受験生の過ごし方を知りたい方向け。この記事では、高校受験の指導歴19年の筆者が、志望校の過去問を解き始めるタイミングなど、受験生の冬休みの過ごし方について解説しています。
よくある質問:中3の夏休みに赤本を解いてもいいですか?
もちろん構いませんが、赤本を使った勉強は夏休みの受験勉強には適しません。
先ほども触れた通り、赤本には中3の2学期や3学期に学習する内容が含まれるからです。
また、中1からの総復習や9月以降の模試に向けた準備など、夏休みにすべきことが他にもたくさんあるからです。
なお、夏休みの受験勉強の内容について詳しく知りたい方は、「【中3夏休み】塾に行かない受験生のおすすめ勉強法【問題集も紹介】」の記事をどうぞ。
【中3夏休み】塾に行かない受験生のおすすめ勉強法【問題集も紹介】
「塾に行かない受験生」の中3夏休みの勉強法と問題集を知りたい受験生向け。この記事では、高校受験の指導歴19年の筆者が、自分でできる、おすすめの中3夏休みの勉強法について解説しています。
【何年分解く?】過去問・赤本のおすすめの使い方

ここからは、過去問・赤本のおすすめの使い方について解説していきます。
おすすめの使い方【ポイントは3つ】
- ポイント①:赤本に直接ではなく、ノートに解く
- ポイント②:5年分を3回繰り返して解く
- ポイント③:不正解だった問題の解き直しをする
上記の3つのポイントを押さえつつ、赤本を使うのがおすすめです。
それぞれのポイントについて、詳しく解説していきます。
ポイント①:赤本に直接ではなく、ノートに解く
ポイント②でも解説しますが、赤本は9割を正解できるまでやり込むことが合格への秘訣です。
そこで、2回、3回と解くことを想定して、赤本に直接ではなく、ノートに解きます。計算やメモは赤本に直接書いても構いませんが、後で消しゴムで消せる程度にしましょう。
丸付け・採点をして点数を記録しよう
赤本の巻末に答案用紙があり、出版社が想定した配点が載っています。
この配点を参考に採点します。
「点数一覧表」を作ると、モチベーションにも繋がるのでおすすめですよ。
ポイント②:5年分を3回繰り返して解く
入学試験の内容は、学校によって特徴や出題傾向があります。
その特徴や出題傾向を完璧に把握して入学試験にのぞむことで、ライバルに大きな差をつけれられることは言うまでもありません。
そこで、赤本は5年分を3回繰り返して解き、9割以上を正解できるまでやり込んでください。
1回目はほとんど解けなくてよい
赤本を解いてみると思ったよりも難しく、ほとんど解けないことも珍しくありません。
しかし、1回目はほとんど解けなくても構いません。ほとんどの受験生が半分も正解できません。
そして、たとえ1回目はほとんど解けなくても、3回目で9割以上を正解できるようになることは十分に可能です。
試験時間を計るのは3回目だけでよい
赤本を解く際、試験時間を計るのは最後の3回目だけで構いません。
その理由は、
- 1回目:ほとんど解けないので、試験時間が余るから
- 2回目:1回目からの学力アップを確認することが目的だから
の2点です。
特に、2回目は1回目からの学力アップを確認したいので、時間を気にしてはいけません。すべての問題を解けるかどうか確認します。
ちなみに、試験時間を意識しながら解く練習は、模試で鍛えればいいのでそこまで心配しなくて構いません。
ポイント③:不正解だった問題の解き直しをする
たとえ赤本を3回繰り返して解いたとしても、ただ解いているだけでは9割以上を正解できるようにはなりません。
不正解だった問題をノートに解き直し、解き方を習得したり、重要語句を暗記しなければいけません。
「解き直しノート」を作ろう!
赤本を解いて不正解だった問題は、ノートに解き直しをして、毎日見直します。
そうすることで、2回目、3回目に点数が上がっていきます。
なお、「解き直しノート」の作り方は「【高校受験】模試・過去問の「解き直しノート」の作り方【簡単です】」の記事で解説しています。
【高校受験】模試・過去問の「解き直しノート」の作り方【簡単です】
高校受験の模試や過去問の「解き直しノート」の作り方を知りたい方向け。この記事では、高校受験の指導歴19年の筆者が実際に受験生に指導している、「解き直しノート」の作り方について解説しています。
【筆者イチオシ!】高校受験におすすめな過去問題集2選

ここからは、筆者が高校受験におすすめする過去問題集2選を紹介します。
これから過去問題集を購入する方は、ぜひ参考にしてみてください。
おすすめ過去問題集2選
- おすすめ①:英俊社「高校別入試対策シリーズ」
- おすすめ②:教英出版「高校別入試過去問題集」
おすすめ①:英俊社「高校別入試対策シリーズ」(問題集タイプ)
通称「赤本」と呼ばれる過去問題集です。
B5サイズの問題集で、学校別に直近の5年~6年分の入試問題が収録されています。取り外し可能な冊子タイプの答案用紙が付いています。
また、英俊社が作成した模範解答と解説も付いています。ただし、解説は簡素なため、受験生自身が解説を使って復習するには少し不親切な印象です。
おすすめ②:教英出版「高校別入試過去問題集」(プリントタイプ)
実際の入学試験で使用される問題用紙と同じ、プリントタイプの過去問題集です。
5年分の過去問(問題用紙・答案用紙)を年度別にB4サイズのプリントで綴じて収録しています。問題用紙と同じプリントタイプのため、より実際の試験をイメージしやすいかと思います。
まとめ

といわけで、今回は以上です。
志望校の過去問・赤本のおすすめの使い方について解説しました。
なお、この記事で紹介した赤本の使い方は、筆者の指導内容そのものです。あとは、みなさんがやりやすいようにアレンジしてみてください。
繰り返しになりますが、赤本は5年分を3回繰り返し、9割以上を正解できるまでやり込むことが合格への秘訣です。
なかなかハードだなぁ…と思うかもしれませんが、それをやり切った受験生はほとんどが合格します。もっと言えば、過去問のやり込み具合が甘い受験生ほど失敗します。
「過去問のやり込み具合なら、誰にも負けない!」
入学試験の当日に、そう思えることを願っています。
「解き直しノート」の作り方
【高校受験】模試・過去問の「解き直しノート」の作り方【簡単です】
高校受験の模試や過去問の「解き直しノート」の作り方を知りたい方向け。この記事では、高校受験の指導歴19年の筆者が実際に受験生に指導している、「解き直しノート」の作り方について解説しています。
過去問が解けない時の対処法
【高校受験】志望校の過去問が解けない時の3つの対処法
「入学試験の過去問を解いてみたら難しくて解けません…」←このような受験生は珍しくありません。この記事では、過去問が解けない理由と、その対処法について解説しています。
中3受験生:冬休みの過ごし方
【高校受験】中3受験生の冬休みの過ごし方【おすすめ勉強法も解説】
中3冬休みの受験生の過ごし方を知りたい方向け。この記事では、高校受験の指導歴19年の筆者が、志望校の過去問を解き始めるタイミングなど、受験生の冬休みの過ごし方について解説しています。










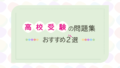

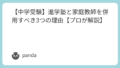
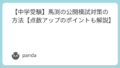

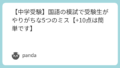



コメント