
次回の公開テストでは、どの単元が出題されるのかしら…。少しでも絞れるなら、公開テスト対策がしやすくなりそう。理科の出題範囲を予想する方法を教えてください。
このような疑問にお答えします。
この記事の内容
- 【公開テスト】理科の出題範囲を予想する方法を公開します
この記事を書いている筆者は、家庭教師での公開テスト対策の指導歴19年ほど。これまでに、100人以上の浜学園生を指導してきました。
この記事では、そんな筆者が実際に行なっている、理科の出題範囲を予想する方法を公開します。
※浜学園の公開テストを例に解説しますが、他の進学塾でも同じ方法で理科の出題範囲を予想できます。ぜひ、参考にしてみてください。
【公開テスト】理科の出題範囲を予想する方法を公開します

早速ですが、筆者が実際に行っている理科の出題範囲を予想する方法を公開します。
※この記事を書いているのが2020年6月8日ですので、ちょうど1週間後の公開テストの出題範囲を予想することになります。
出題範囲を予想する手順
- 手順①:既に出題された単元を確認する
- 手順②:既に出題された単元を除外する
- 手順③:直近の学習単元を除外する
- 手順④:未出題単元を分野ごとに分類する
手順ごとに詳しく解説していきます。
手順①:既に出題された単元を確認する
まずは、これまでの公開テストで既に出題された単元を確認します。
これまでに受験した今年度の公開テストをすべて手元にそろえます。そして、出題された単元を下のような表にまとめていきます。
※ただし、大問1の正誤問題を除いた大問2~5の4題のみで結構です。
| 分野 | 実施回 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
| 学習内容 | 563回 | 564回 | 565回 | 566回 | |
| 生物 | 生物・植物 | 花のつくり | |||
| 生物・動物 | こん虫 | 動物総合 | |||
| 人体 | 消化と吸収 | ||||
| 地学 | 天体 | 月の動き | 星の動き | 太陽の動き | |
| 気象 | 気団と前線 | ||||
| 物理 | エネルギー | 光の性質 | |||
| 電気回路 | 豆電球 | ||||
| 力学 | おもりと運動 | てこ | |||
| 化学 | エネルギー | 水の状態変化 | 熱の伝わり方 | ||
| 物質の性質 | もののとけ方 | ||||
| 反応 | 気体の発生 |
表にまとめる際の注意点
- 生物、地学、物理、化学の4分野に分ける
- 学習内容は各分野3つまでに分ける
上記の2点に注意しながら、これまでの公開テストで出題された単元をまとめます。
ちなみに、2020年の2月(563回)~5月(566回)については、筆者が作成した上の表をそのままお使いください。
この表を使って、次回の6月(567回)の出題範囲を予想します。
手順②:既に出題された単元を除外する
続いて、次回の公開テストで出題されそうな単元を予想していきます。
まずは、手順①で表に記入した「既に出題された単元」を予想から外します。
というわけで、今年度の公開テストで「既に出題された単元」を予想から外します。
なお、2020年度の出題結果をまとめた「【浜学園公開テスト小6理科】8月までの出題傾向と9月以降の対策」の記事が参考になります。気になる方はどうぞ。
【浜学園公開テスト小6理科】8月までの出題傾向と9月以降の対策
2020年度の浜学園公開テストも、志望校を判定するために重要な9月、10月、11月を迎えます。この記事では、そんな公開テストの9月以降の対策として、小6・理科の8月までに出題された単元と、まだ出題されていない単元をまとめています。
手順③:直近の学習単元を除外する
次に、習ったばかりの単元や、現在学習中の単元を予想から外します。
その理由は、授業で学習した単元は、その2〜3カ月後の公開テストで出題されるからです。
というわけで、習ったばかりの単元と現在学習中の単元を予想から外します。
ちなみに、次回の公開テストでは、下記の単元を予想から外しました。
- 力学:かっ車と輪軸
- 反応:酸とアルカリ
- 地質:地層のでき方
- 物理:浮力
手順④:未出題単元を分野ごとに分類する
手順①で作成した表から、ある傾向が読み取れます。
それは、生物、地学、物理、化学の4つの分野から1題ずつ出題されていることです。
そこで、まだ出題されていない単元を分野別に表にまとめてみます。
| 生物 | 地学 | 物理 | 化学 |
| ・種子の発芽・光合成 | ・星と星座・星座早見 | ・音のはたらき | ・水溶液のこさ |
| ・根・茎・葉のつくり | ・雲のでき方 | ・ばねとものの重さ | ・二酸化炭素の性質 |
| ・メダカ | ・日本の天気 | ・ふりことおもり | |
| ・肺と心臓 | ・流水の3作用 | ||
| ・血液とその循環 | ・地層とその変化 | ||
| ・骨と筋肉 |
表にまとめてみると、各分野1~6個の単元まで絞ることができました。
この中から、各分野から1単元ずつ出題される可能性が高いと予想できます。
以上が、筆者が実際に行なっている、理科の出題範囲を予想する方法です。
要注意!山を張りすぎるのは危険です
今回の記事では、今年度の公開テストで既に出題された単元や、最近習ったばかりの単元を外すなどして、出題が予想される単元を18個まで絞りました。
ここから、さらに絞ることも可能ですが、個人的にはあまりおすすめしません。
その理由は、山を張りすぎると予想が外れた時に散々な結果に終わる恐れがあるからです。
まとめ

というわけで、今回は以上です。
筆者が実際に行なっている、公開テストの理科の出題範囲を予想する方法を公開しました。
公開テストの出題範囲の予想は、必ずしもしなければいけないわけではありません。それでも、やみくもに勉強するのではなく、出題されそうな単元に絞って勉強することで、点数アップに繋がるかと思います。
この記事の内容が、少しでも参考になれば幸いです。
なお、自分でできる公開テスト対策の方法は、下記の記事にまとめています。
【浜学園公開テスト対策】公開テストの点数を上げる方法【プロが解説】
浜学園の公開テスト対策の指導歴19年の筆者が、公開テストの点数を上げる方法をまとめました。①点数が上がらない理由・②点数アップの解き方・③自分でできる公開テスト対策の方法、の3つです。

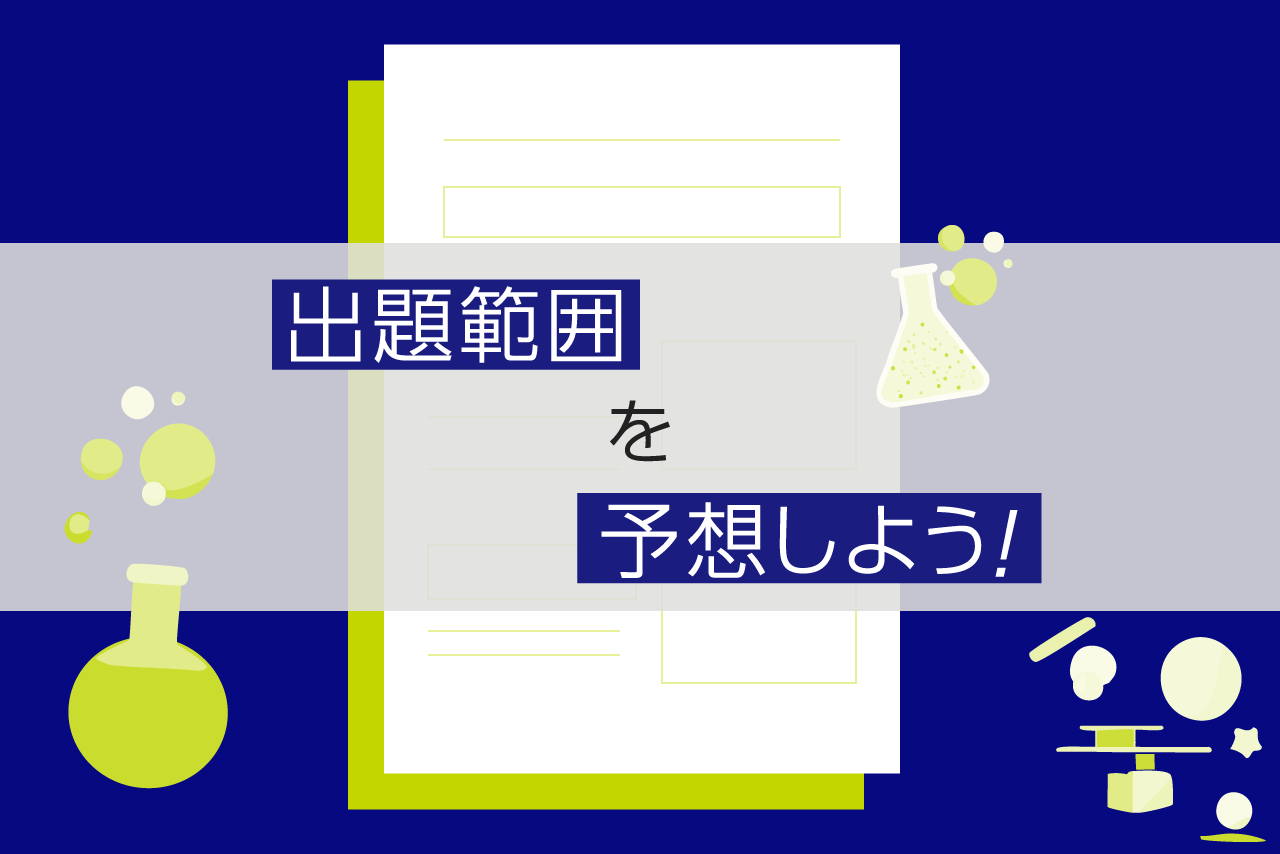



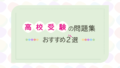

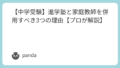
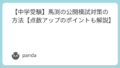

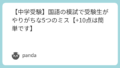




コメント